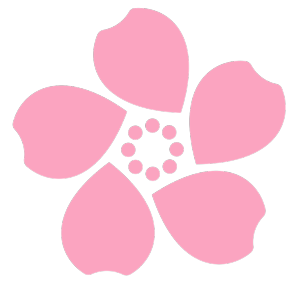 産廃コンサルティング
産廃コンサルティング

廃棄物コンサルタント事業本部
本部長 加藤 隆也
【略歴】
1979年 筑波大学生物環境造成学科卒
1979年~2004年 日本技術開発(株)勤務 環境施設部長で退職
2004年~ ウエストマネジメントコンサルタント設立
2021年~ (株)さくら 廃棄物処理事業本部長
【資格】
工学博士
技術士(衛生工学部門)(総合技術監理部門)
一級土木施工管理技士
最終処分場機能検査者(全部門)
【経歴】
建設コンサルタントでの一級廃棄物処分場計画設計の経験を経て、現在は産業廃棄物処分場を中心に、最終処分場の計画・設計・許認可取得・施工監理・維持管理指導に40年以上従事しており、担当した処分場は100件を超える。
NPO法人 環境技術支援ネットワーク理事
【主な実績】
三和技研工業(株)安定型処分場拡張許可取得業務(山口県)
(株)北陸環境サービス管理型最終処分場 設計、許可取得、施工監理業務(福井県)
(株)環境クリーン管理型最終処分場 設計、許可取得、施工監理業務(岡山県)
(株)青森クリーン管理型最終処分場 設計、許可取得業務(青森県)
青森岩手県境不法投棄除去事業排水処理計画業務(岩手県委託)
ハノイ市福岡方式廃棄物最終処分場支援業務(福岡県委託)
 地球温暖化に優しい最終処分
地球温暖化に優しい最終処分
SDGsって、皆さんもよく見かける言葉ですよね。「持続可能な開発目標」のことです。
弊社でも独自のSDGsを掲げて、努力をしています。
「最も持続可能でないといけないもの」って何でしょう?
ずばり「私達が生存できる地球環境」のことではないでしょうか。
すると一番の問題は「温暖化による気象変動」です。既に全世界で、目に見える気象変動が起こっていて、大きな被害がでていることは皆さんも心配していますよね。
この「温暖化」の原因といわれるのが、温室効果ガス、特に身近に排出されるCO2です。
現在多くの国は、CO2の削減に必死で取り組んでいます。私たちの廃棄物処理の世界では、3RがSDGsに対する具体的な取り組みとされてきました。
3Rとは、「リデュ―ス(削減)」「リユース(再使用)」「リサイクル(再利用)」のことです。
特にこれまでは「リサイクル」が花形として、多くの廃棄物が処理されています。
特に廃プラスチックが中間処理され、固形燃料として火力発電に使用されるシステムが「リサイクルの優等生」でした。
一方、最終処分はそのまま埋めてしまうのですから、リサイクルの観点では「劣等生」です。
これまでは日本の経済界も自社の廃棄物のうちリサイクルに回る率を「リサイクル率」と言って、この数値が高いから環境に配慮した企業だと言ってきました。
ところが、実際にはこの「リサイクル」をするために発生するのCO2の量やリサイクル物を使用する際に発生するCO2量はカウントされておらず、「CO2排出量」ではなく、「リサイクル率」のみ評価をしてきたというのが、現実です。
私達の仕事である最終処分では、基本的に処分自体でCO2を発生させることはありません。
作業における重機の稼働等でCO2を発生させますが、その量は他の処分場と比べて極めて小さいものです。
温室効果ガスの排出の観点から適正な3Rが選択されれば、最終処分場の役割がより重要になります。
実は、最終処分は温暖化防止の優等生なのです。
技術顧問:加藤隆也
 三和の処分場は脱炭素施設
三和の処分場は脱炭素施設
これまで廃棄物をリサイクルすることが、環境にとって一番いいこととされて来ました。最終処分場はリサイクルできないものを埋立処分する施設と言われて来ました。
しかし今日、世界は単にリサイクルではなく、脱炭素戦略(GX)をより早く、より強力に進めていかなくてはならない状況です。勿論我が国においても早急な脱炭素移行が求められています。現在廃プラスチックの多くは、RPFと呼ばれる燃料に中間処理されて、それを焼却した燃焼熱を利用して発電をするリサイクルシステム(サーマルリサイクル)が主流です。しかしこのシステムではリサイクルの過程で、多くの二酸化炭素を排出してしまいます。現在の我が国においては、このサーマルリサイクルもリサイクルとしてカウントされていますが、欧米では既にサーマルリサイクルはリサイクルの枠からはずされています。
化石燃料を使用して、新たにプラスチックを製造する量は、今後大幅に減り、材料自体のリサイクル(マテリアルリサイクル)とプラスチック代替材料の開発に変わっていきます。市場に余っている過剰なプラスチックの脱炭素戦略に最も貢献できるのが、安定型最終処分場です。最終処分場に適正に処分されたプラスチックからは、二酸化炭素は排出されません。
三和の処分場は廃プラスチックの適正処理は勿論、 法令より厳しい水質基準を設定している脱炭素戦略優等生です。
 こんなことはありませんか?
こんなことはありませんか?
~我々のお客様~
技術的な専門家や法律の専門家を自社内に持っていない廃棄物処理に係わる中小企業で、真面目に仕事をしていて困っている方たちです。
我々ができること
-
真面目に事業をしているのに、行政との意思疎通がうまく行かず、無理な指導を受けたり、こち らの意見を聞いてもらえない。
-
こちらの主張や行政の意見の技術的法的妥当性を検証して、最適な方向性と具体的な対応を示したうえで、行政と協議を行い、最善の着地点を決定します。
-
施設管理において、こんな問題がでてきているが、技術的な対応がわからない。
-
施設の現況を調査して、問題の原因と対策を立案します。具体的な設備の改造等のアドバイスも可能です。
-
最終処分場の残容量が少なくなって来たので、今後の計画を考えないといけない。
-
現処分場の延命化や拡張、次期処分場計画の立案等埋立完了までのスケジュールを考え事業が中断しないような、作戦をたてましょう。
-
施設の設置許可の手続きを行っているが、一向に進まない。行政との協議もやってはいるが、具体的に進んでいるのかもわからない。
-
これまで提出している書類や協議内容から、行政が現時点で、どのように考えているかを判断します。
事業者は長い間協議しているので、手続きが進んでいると思っている場合が多いですが、実は行政的には何も進んでいないといういことも結構あります。コンサルタントに任せている からではなくて、客観的に現状を判断しましょう。その上で今後の作戦をたてましょう。
-
行政との技術的な協議は行っているが、技術的な協議、交渉をできる人材がいない。コンサルタントに任せているが、不安である。行政から技術的にわかる人をつれてこいと言われた。
-
今の計画の問題点を含めて検証したうえで、行政が納得し、かつ事業者にとって最善の方法を示して、行政と交渉します。現在のコンサルタントに技術的な指導を行い、早期に正しい着地点に導きます。
-
ゼネコンに工事を任せているが、品質管理や使用前検査対応等心配だ。
-
定期的な現場監理を行い、使用前検査を想定した、品質や出来形管理を実施させます。当然事前の行政との協議もやっておかないといけません。
